
アフリカの稲作の現状と課題
1.アフリカの稲作の現状
サブサハラ・アフリカ(サハラ砂漠以南のアフリカ諸国、以下アフリカと呼ぶ)のコメ生産は、1960年の200万トンから2007年には910万トンへと着実に増加してきた。一方、消費はこの間に200万トンから1680万トンへと急増し、アフリカ全人口の5割が年間10kgのコメを消費している計算になる。現在の輸入量は770万トン(約23億ドル)とされており、今後とも都市化の進展に伴って、他の穀物に比べて、調理が比較的簡単で、栄養価に富み、食味のよいコメの消費はさらに伸びていくことが予想され、その生産増強はアフリカの各国にとって大きな課題となっている。
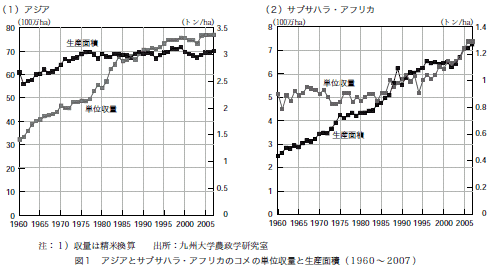
図1に示すように、60年以降、アジアの稲作は、「緑の革命」と呼ばれる新品種の導入、灌漑の整備、化学肥料の投入によって、単位収量が1.3トン/haから3.4トン/haへと、大きく伸びたことによって支えられた。一方、アフリカの生産増は栽培面積の拡大によってもたらされたもので、単位収量は現在でも1.2トン程度とアジアの五十年ほど前の数値に留まっている。アフリカ大陸の3分の2以上は乾燥地、半乾燥地であり、必ずしもコメの生産に適していないこと、また稲作に適した内陸低湿地は、貴重な動植物の保護の観点などから、大規模な耕地化が期待される地域は限られている。したがって、今後のアフリカのコメの増産は、天水畑作の単位収量を上げることと、小規模な内陸低湿地の活用がカギとなろう。
2.わが国の協力の経緯

写真1 ウガンダにおけるネリカ4番の栽培風景(2006年 坪井撮影)
わが国は、70年代以降、アフリカ各地で灌漑稲作技術の開発と普及協力を実施してきた。無償・有償資金協力によって、モデル灌漑地区の整備や研修センターを設置するとともに、専門家チームを派遣し、技術協力を実施した。その結果、タンザニアのローアモシ地区やケニアのムエア地区などは、アジア並みの単位収量を確保するに至り、紆余曲折を経ながらも現在では、それぞれコメの一大生産地を形成している。また、技術協力の拠点となった各技術センターでは、多くの技術者が養成されるとともに、栽培マニュアルも整備され、それぞれの国の灌漑稲作全体の底上げに重要な役割を果たしてきた。
稲作技術の農民への普及に当たっては、モデル灌漑地区の展示圃場を活用し、地域のリーダー的な農家に基本的な技術(育苗、条植え、除草など)を移転し、その農家が周辺農家に移転していくという農民間普及の手法を取り入れてきた。また、集約的な灌漑稲作へ移行するに当たっては、農業機械の導入による適切な作業効率の向上と、肥料投入も重要である。これらについても、食料増産援助を中心とした支援を実施し、技術協力の効果を拡大した。
わが国以外では、60年代以降、西アフリカを中心に、フランス、北朝鮮、中国、台湾などが、各地に大規模な灌漑稲作施設をつくり、技術協力を実施してきた。
80年代の後半になると、各地の大規模灌漑施設の老朽化が進むとともに、構造調整政策のもと、施設管理に携わる政府職員の数は大幅に削減された。その結果、灌漑施設の管理を原則として農民団体に移管する「参加型水管理」導入の必要性が高まった。わが国はガーナなどにおいて、水利組合の形成や能力強化を目的とした技術協力を実施し、アフリカにおける参加型水管理の普及に一定の役割を果たした。
90年代後半以降、援助の潮流は貧困削減、食料の安全保障に大きくシフトし、貧しい小規模農家が自分たちで計画から施工、管理までできる、小規模な灌漑稲作への協力が一般的となってきた。
92年に西アフリカ稲開発協会(WARDA)において、アジアイネとアフリカイネの交雑種(2000年に「ネリカ」と命名された)が開発されてからは、アフリカにおける稲作開発の可能性が大きく拡大した。わが国はネリカの開発を資金面でも技術面でも支えてきた。03年のTICADⅢにおいても、「ネリカ」の普及をアフリカ農業支援の重点項目として掲げた。現在はWARDAおよびウガンダへの専門家派遣を中心に、積極的な支援が行われている。
3.ネリカ普及支援
アフリカのイネは、WARDAの分類によれば、灌漑水田、天水低湿地、天水畑のほか一部にはマングローブスワンプ(低湿地)、深水地帯で栽培されている。イネの全耕作面積760万haのうち灌漑水田は15%、マングローブスワンプと深水地帯と合わせて5%程度とみられ、残り80%が天水低湿地と天水畑である。天水のうち、畑の方が低湿地よりやや多いとされる。いずれにしても、稲作の80%は不安定な降雨に頼った、粗放的な栽培に留まっている。
稲の栽培上、土壌水分と窒素分の豊かさから低湿地の方がポテンシャルに富んでいるが、作業効率の低さ、洪水と干ばつの繰り返し、鉄過剰、イネ黄斑病、アフリカ・イネノシントメタマバエといった病害虫の発生といった問題点を抱えている。一方、天水畑では、作業効率は比較的よいが、干ばつ、雑草との競合、低肥沃度、イモチ病の発生といった問題を抱えている。こうした条件下のアフリカの貧困農民のために、WARDAは天水稲作のための品種改良に取り組み、92年、育種担当のモンティー・ジョーンズ博士が、収量の高いアジアイネ(オリザ・サティバ)と、粗放栽培にも適合し、雑草競合に優れ、イネ黄斑病やアフリカ・イネノシントメタマバエに強いとされるアフリカイネ(オリザ・グラベリマ)の種間交雑から、稔実性のある個体を作出することに成功した。2000年には種間交雑のうち、WAB450シリーズのなかから、有望な7品種をWARDAは推奨品種として各国に配ったが、この際この品種群を「ネリカ」(New RICE for Africaの略称NERICA)と命名した。現在では「ネリカ」と呼ばれるものは、陸稲種が1番から18番まで、水稲種が1番から60番まである。
水稲ネリカは比較的最近になって開発されたもので、その品種特性など明らかでなく、アフリカのイネにとって大敵であるイネ黄斑病に耐性がないことなどから、今後の研究に待つ部分が多い。
一方、陸稲ネリカでは、各国によって差があるが、1、2、4、8、10番が比較的好評である。筆者が勤務しているウガンダでは1番(香りがある)、4番(収量が多い)、10番(早稲)を奨励品種として国が定め、現在3万haまで普及が進んでいる。しかし、アフリカ各国で普及レベルに達していることが確認されているのは、ウガンダのほかは、ギニア、コートジボアール、マリ、エチオピアで、それ以外の国では試験研究所およびその周辺で若干普及されているにすぎない。
この原因として一番大きなものは、アフリカの各国の試験研究所では、イネの専門家がほとんどおらず、またその専門家も育種家がほとんどで、「ネリカ」と他の品種から新しい自分の「ネリカ」を作ることに興味を持っており、それぞれの国において、既存のネリカの品種特性を明らかにしたり、栽培技術を開発する研究者はほとんどいないことである。
日本、中国をはじめとするアジアでは、稲作は数百年以上の歴史をもち、農家はイネ栽培に多くの経験と知識を有し、それを支える研究と普及の体制も整っている。一方、アフリカでは西アフリカでもせいぜい百年、東アフリカでは第2次世界大戦後の五十年程度の歴史しかもたず、農家の経験と知識は浅い。したがって、アジアではその栽培の経験と知識のうえに、灌漑、肥料、新品種を投入して起こった「緑の革命」と呼ばれる生産性の向上が、アフリカではまだ起こる背景がなく、革命前夜にすら至ってないと言ってよい。アフリカでは何よりも、それぞれの土地に合った稲作技術の開発と普及が必要である。しかし、普及システムについても世界銀行が主導した構造調整以降、地方分権化、民営化の波のなかに飲み込まれ、十分に機能していないケースがほとんどである。
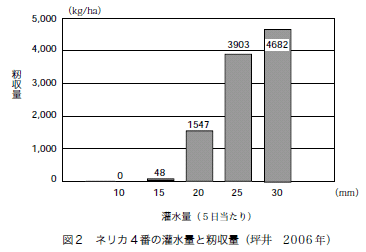
ところで、陸稲ネリカは粗放的で劣悪な条件下にあるアフリカの天水畑の稲作に適合することを目的に選抜されてきたものであるが、イネである以上は成育期間中、一定の土壌水分が確保される必要がある。筆者が勤務しているウガンダのナムロンゲ国立試験場で06年後期の雨期にネリカ4番を用いたスクリーンハウス内実験では、図2に示すように、生育期間中1日当たり最低4mmの灌水量が必要であった。また、この図から分かるように、灌水量が多いほど収量が増加することも確認できる。
さらに、同じくナムロンゲ試験場の天水畑で、04年後期の雨期から始めた、長期施肥・無施肥比較試験では(同一圃場、同一条件)、これまで7回の雨期天水稲作の結果、干ばつの被害が出た05年後期と07年後期の雨期を除けば、無施肥区で1.7トン/ha、施肥区では3.5トン/haを上げている。また、07年後期の雨期に水田で栽培したネリカ1番は6トン/haであった。こういったことから、陸稲ネリカの最大の特徴は、いわば水陸両用であり、粗放的栽培でも土壌水分が確保されれば、一定の成果を上げるが、集約的栽培になればなるほど、いっそうの成果を得る可能性のある品種であるということができる。
4.今後の協力の方向
今後、わが国は、ネリカの開発によって新たな展望が開けたアフリカの稲作開発全般を継続的に支援すべきである。そのためWARDA、国際稲研究所(IRRI)といった国際機関と連携しつつ、各国の国立試験場の稲作研究の能力向上を支援し、これまでに実証された栽培・営農技術と最新技術を組み合わせ、天水畑、天水低湿地、灌漑稲作といった多様な栽培形態に適合する稲作技術の普及を包括的に推進することが重要である。稲作経験の浅い農家に対する普及に当たっては、新品種の導入、播種、施肥、除草といった栽培技術はもとより、適期収穫、脱穀、乾燥といった収穫後処理の指導も必要となる。また、全ての作業が手作業である現状を改善するために耕耘機、播種器、脱穀機などの開発・製造指導も必要である。
栽培技術普及システムの脆弱性を補うため各国に派遣されている、青年海外協力隊の村落開発隊員を活用することも考慮すべきである。また、長期的には、日本およびアフリカの若い人材育成のために、日本の各大学農学系学部の積極的な関与が望まれる。
アフリカの稲作の歴史は新しく、一般の農家が適切な稲作技術を獲得するには、少なくともまだ一世代の試行錯誤の苦闘と、息の長い努力の時代が続くと覚悟したうえで、アフリカと日本、双方の関係者がTICADⅣを機会に、アフリカのコメの自給達成に向けた強い意志を表明すべきである。
たとえば、アフリカの開発を考える場合、研究や情報収集を最初から始めるのではなく、連携や協力により国際水管理研究所(IWMI)を含む国際農業研究協議グループ(CGIAR)傘下の15のセンターの有する経験や知見を活用することが、効率的な資金の利用や、有効な支援、開発に結びつくものと考える。