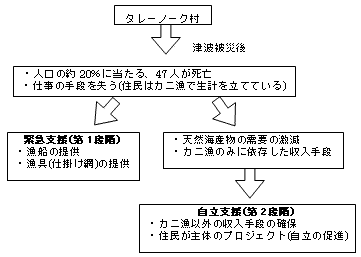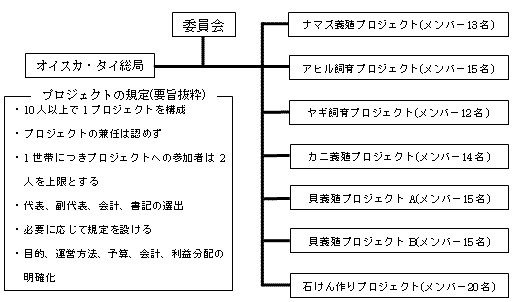〜スマトラ沖地震・津波被災地復興支援から〜
長期的視野に立った復興支援の事例
前オイスカ・タイ総局
ボランティアスタッフ 田野井 智之
はじめに
「TSUNAMI」。
地震国日本に生まれ、太平洋を眼前に育ったにもかかわらず、幸運にも私は、未だにこの国際語を生半可な知識として認識しているに過ぎません。元来、地震がたいへん少なかったタイにおいて、ほとんどの人々はその国際語の存在すら知りませんでした。2004年12月26日までは。

1.復興支援に至った背景
オイスカ(OISCA:Organization for Industrial, Spiritual and Cultural Advancement)は1961年に創設され、現在24の国と地域において農村開発や人材育成、植林などの環境保全活動に従事している国際協力NGOです。タイでは約30年にわたり、農村開発や植林活動、国内各地の子どもたちを対象にした環境教育プログラムに取り組んでいます。
今回の津波被災地復興支援の舞台となったラノーン県では、日本の支援者や地元の行政、そして地域住民の協力の下、2000年から県の中心部にてマングローブ植林プロジェクトを実施しています。日本においては、津波の被災に遭ったそれぞれの国に活動拠点を有しているオイスカに対し、支援機関としての社会的要請が高まったことが必然であれば、タイにおいてもまた、プロジェクトを通した数年来のラノーン県との絆が、ここでの支援を実施させるに至った必然と言えるでしょう。災害復興を専門としていない私たちは、ともかく国内外のそのような背景から、オイスカの特徴を生かした具体的な支援の形態を模索することになったのです。
南北に長いラノーン県はマレー半島の最狭部、クラ地峡の西岸に位置しています。北部から中心部にかけては、半島最大のクラブリ川を隔てミャンマーと国境を接しており、河口地帯には、約1万9600ヘクタールにも及ぶ東南アジア有数のマングローブ林が広がっています。他国同様、このマングローブ林が津波を緩衝する役割を果たし、被害は最小限に食い止められたと言われています。しかし一方で、目の前がアンダマン海に開けている県の南部では、津波の被害に遭った地域が点在していました。私たちは、津波から約1か月後の2005年1月下旬から、この地域の被害調査を開始しました。そして約3週間後、近辺の被災地と比較して、支援活動が最も遅れていたタレーノーク村という小さな漁村での復興支援を決定しました。
2.人道支援の実情と支援地の選定
ラノーン県スクサムラン郡タレーノーク村。津波は、カニ漁で生計を立てている人口223人ののどかなイスラム教の村から、47人の生命を奪いました。電話や観光資源をもたない、陸の孤島とも言えるこの村に、初めて足を踏み入れた時の様相は、報道を通して見るプーケットやクラビなど、観光地のそれとは大きく異なるものでした。食糧、医薬品などの人道支援と政府による被災住宅の建設支援以外に、具体的な支援は遅々として進んでいなかったのです。このことを理解するには、以下のような支援に関する当時の社会背景を説明しなければならないでしょう。
・食糧、医薬品などの人道支援物資は、被災者に比較的スムーズに行きわたった。これはタイ人の相互扶助を重視する国民性に負うところが大きいと思われる。
・プーケットなどの国際的な観光地が被災したこと、また2005年2月に下院の選挙を控えていたことで、政府は国内外に対して、とかく支援に砕身すべきという、より強固な動機付けがあった。
・一方で、援助を目的とした国内外の個人や団体が、それらの観光地を中心に無計画に殺到したため、政府は部外者が被災地へ入ることへの自粛勧告を出していた。
つまりタイ国内での支援に関する問題は、「一定地域への支援の偏り」に尽きると言えます。タレーノークのような寒村は、この偏りの負の影響を受けた典型的な事例でした。
一方で、改めて記述するまでもないことですが、災害時における支援のニーズは、刻一刻と変化をしていきます。今夜はどこに寝ればいいのか、果たして食事にありつけるのだろうか。そうした目の前の困難が解消されると、次は、以前のような日常に戻れるのだろうかという不安に襲われます。さらに飛躍すると、再び将来起こるかもしれない惨事に対して、自らの生活を守る手立てはないのだろうか、という発想もあるでしょう。このように段階的に被災者の不安の質が、長期的な視野へと移行するところにこそ、私たちの力を発揮できる舞台があると考えたわけです。
加えて何よりも重要なことは、一過性でない復興支援を実施するに当たっての主体者として、住民が自活に向けた意識を共有しているか、ということです。タレーノーク村の場合、日常に戻ることはカニ漁へ復帰することでした。そして自らの生活を守る手立ては、カニ漁のみに依存しない新たな収入手段の確保であり、このことは津波被災以前から、住民の悲願でもありました。長年にわたり農村開発を手がけてきたオイスカへのニーズは、まさにここにあったのです。
3.2段階の支援計画
このような考えの下、私たちは支援を2段階に分けて実施する計画を立てました(図1参照)。第1段階では、住民がカニ漁の際に使用する漁船と漁具の支援を、第2段階では、新たな収入手段を確保する副業づくり支援を、それぞれ「緊急支援」、「自立支援」と位置付けて実施するに至ったのです。まず始めに、第1段階の「緊急支援」について説明していきましょう。
3−1 緊急支援
一口に漁船を提供するといっても、その方法はいくつか挙げられます。資金を提供して各々の住民が業者に発注するのか、あるいは、私たちが必要総数を取りまとめた上で発注するのか。今回のケースでは、後者が採用されましたが、それは、同じように津波で被災した近辺の漁村での事例を参考に決断されました。漁業が唯一の主要産業であるこの地域では、タレーノーク村と同じように、漁船を失った住民が数多く存在していました。政府やNGOなどから、そういった住民に対し漁船の建造費用の支援が行われましたが、残念なことに一部で、材料となる木材などの不当な価格高騰が起きたのです。また、特に公的な支援金が、被災者の手元に届く過程で搾取が行われるという、アジア的な現実も見られました。こうした状況のなかで、心ならずも必要以上の資金を申請する被災者も現れ、その慎重な審査のために、支援が遅れる悪循環に陥っていたのです。
そこで私たちは、漁船を失った当事者に対し、漁船登録証の提示を条件に聞き取り調査を実施する、二重の確認作業を行った上で、必要な総数を業者に発注することにしました。こういった建設的な運営体制を構築したことで、建造単価を抑えられただけでなく、発注総数34艘中、実に28艘は、現地を訪れたオイスカ以外の団体や個人からの賛同により、建造資金がつくられることになったのです。同様の過程を経て、漁具は1艘につき100個(合計3400個)の仕掛け網を現物支給しました。余談ですが、漁船の塗装作業などに住民が積極的に参加した結果、この地域が長い雨期に突入する4月を前に、第1段階となる緊急支援を終了することができました。早期の漁へ復帰は、早期の日常への復帰でもあるのです。
3−2 自立支援に向けての体制づくり
この原稿を書いている今、イスラエルとレバノンの国境付近では、寸鉄を帯びていない人たちが、空爆や銃砲によって命を落としています。アメリカ南部がハリケーンによって壊滅的な被害を受けたのは、つい1年前のことでした。このような惨事が様々な形でメディアに取り上げられると、国際的な人道支援がそこに集中します。それでも、きっといつかは再び平穏が訪れ、そしていつの間にか、人々の記憶から風化していくことでしょう。驚くことに私たちは、こういったに現実に、あまりにも鈍感になっていることに気付いていません。
そもそも「人道主義」という言葉の意味は、人類全体の幸福を増進しようとする立場であるといわれています。したがって今日の人道支援の姿が、日々の食料を与え、物質や目に見えるインフラなどの原状回復をするだけでは、不完全であることが見えてくるような気がします。タレーノーク村において、第1段階の緊急支援を終え、第2段階の自立支援に移ることは、私たち自身が考える「人道支援」の始まりである、と捉えられるのです。
そこで早速、副職づくりを進めるプロジェクトの具体的な枠組みの検討に入ったのですが、私たちはここで、思わぬほど時間を費やすことになりました。この原因は、一つに意思伝達の不手際が挙げられます。第2段階の支援では、プロジェクトの受益対象者が、緊急支援よりも更に広く、かつ、公正さが求められなければなりません。にもかかわらず、私たちは主に村長や村の主だった人々を通しての情報提供に頼り過ぎたがために、全ての住民に対し、枠組みの意図が明確に伝わらなかったのです。このことは同時に、より多くの住民の声を自立支援に反映させる、という点においても不都合なことでした。これが二つ目の原因です。私たちは枠組みを検討する前に、枠組みを検討する体制から再考しなければならないことに気付かされたのです。「急がば回れ」。意思伝達の効率性に、気をとられてしまった結果でした。
この反省を生かすべく、私たちはまずオイスカ役員、地方行政官、獣医、タレーノーク村の村長など、合計7名からなる委員会を組織し、自立支援におけるオイスカの意思決定機関としました。したがって、オイスカ側から住民への意思伝達は、この委員会の名を以って行われることで一本化されたのです。同時に、特定の人物を介することなく、全員参加型の会議を実施したことで、情報提供がより明確化されました。こうして、自立支援の枠組みが形作られることになったのです。緊急支援が終了してから、実に3か月以上もの月日が流れていました。
3−3 自立支援と「小さなNGO」の役割
この自立支援の最大の特徴は、一定のルールの下、副職づくりの具体的な実施計画や運営そのものを住民に委ね、より主体性を高めた体制を採用しているところにあります。これに伴い委員会は、住民たちによって企画されたプログラムの精査・承認、資金供与、プロジェクト運営時におけるアドバイスと監査およびプロジェクトの評価に専心することとなりました。プロジェクトパートナーとしての委員会(=オイスカ)の役割を最小限に抑え、プロジェクト、ひいては住民の自立性をより高めることに焦点を置いたのです。私たちのこの役割は、さながら市場経済で言う「小さな政府」ならぬ、「小さなNGO」であると言えるでしょう。
こうして住民による副職づくりプロジェクトが自らの手で企画され、6プロジェクト7グループに対し、委員会からの承認が得られました(図2参照)。2005年8月、これらのプロジェクトは、順次開始されたのです。
石けん作りを除いた各プロジェクトは、タイでは食用として需要の高いものばかりです。村内の就労人口の7割以上が参加しているこれらのプロジェクトの仔細を述べることは、主題と離れるのでここでは割愛します。しかし運営過程において、メンバー同士の話し合いや意見の交換は頻繁に行われ、結果は様々な形で具体化されました。
一例を挙げると、孵化直前のアヒルの卵を、他のアヒルがつついてしまう問題が発生した際、メンバーは自ら資金を拠出し合い、簡易柵を設置し、母親と卵を他のアヒルから隔離する対策を採りました。また、残菜や鶏の内臓を近くの市場から無償で調達し、ナマズの餌代の抑制を図る、というアイディアも実行されました。このように問題発生時の対応、運営コスト削減、必要に応じての自己資金の拠出など、試行錯誤を繰り返しながら、住民の自立促進という大義が、実に的確な方向に進んでいると感じる瞬間が多々ありました。ところで、こういった各プロジェクトの現況を把握するには、パトロール(現地への訪問確認)と食事(メンバーとの対話)が欠かせません。何ともお笑い種ですが、私自身もせっせと現地に通い、その都度メンバーから食事をご馳走になっては、「小さなNGO」の数少ない重要な任務を果たそうと、努めたものです。
 |
 |
| 写真2 漁船の塗装作業を手伝う住民。オイスカからの支援6艘と合わせて、計34艘の支援を行った | 写真3 石けん作りプロジェクトの様子。受注量に基づいて生産が行われている |
3−4 自立支援の成果
2005年12月、ナマズの販売を皮切りに、いくつかのプロジェクトで収入が得られるようになりました。しかし敢えてここで特筆したいのは、水位調節の失敗が原因で散々な結果となったカニ養殖プロジェクトについてです。メンバーはもちろん、この結果に対してひどく気を落としていましたが、その現実を受け入れ、原因を議論し合い、その反省を踏まえた次なる目標を委員会に表明しました。この種の支援の評価の在り方を巡っては、様々な指標が挙げられるでしょう。しかし私たちは、実際的な収入と共に、失敗を糧へと繋げる姿勢をメンバーが見せてくれたことさえも、成果として誇れることだと思っています。なぜならこれは、住民の自立支援だから。

4.復興の意義について
お気付きかもしれませんが、今回の復興支援において難儀したのは、その運営段階よりも、むしろ創成期であったと言えます。しかし、この時期にしっかりとした準備ができないと、支援自体が単なるパフォーマンスに終始してしまうことも、可能性としてあったわけです。支援に直接・間接的に携わった全ての人々の微衷を無駄にしないこと、そして何よりも、支援は被災者を第一に考えなければならないことを、私たち自身も体験的に学ぶこととなりました。
「何を以って復興なのか?」。この命題に対し、恥ずかしながら、未だに自信を持って答えることのできない自分がいることに、改めて気付かされます。タレーノーク村は、いつかきっと復興するでしょう。倒された木々も小さな瓦礫でさえも、全ては片付けられ、日々の暮らしはすっかり落ち着きを取り戻し、村は立ち直るに違いありません。しかしそれは、以前とまったく同じタレーノーク村の姿なのか。決してそうではないでしょう。津波と不本意にも復興に携わった全ての人々は、この村を永遠に変えてしまったのです。それでも私たちは、このことを決して悲観視してもいません。絶望を乗り越えた住民たちの、これからの営みがある限り、タレーノーク村はきっと新しく生まれ変わるに違いありません。ここでの軌跡は“復興”という過去に固執したことではなく、“創造”という希望を伴った言葉に置き換えるべきものなのかもしれません。