
アジアのコメ生産性―到達点と増収可能性
1.はじめに
産業化と都市化の進行および不適切な耕地管理などに起因する、優良農地の減少と土壌劣化が世界各地で進行している。コメ生産の大部分を担うアジアでは、今後、耕地として利用が可能な土地が他の地域よりも限られている。とりわけ南アジア地域では耕作適地の利用が限界に達し、農業生産のかなりの部分が持続的生産に適さない土地に及んでいるという(Penning
de Vries、2001)。このような状況のもと、イネ生産力の今後は、土地生産性の増大に大きくかかっている。
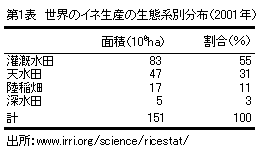
稲作は灌漑稲作と自然の降雨に依存する天水稲作に大別されるが、後者にはさらに畦を高くした水田で営まれる天水田栽培、畑状態で稲を栽培する陸稲栽培および雨期後半に水深が1mにも達する深水稲作に分けられる(表1)。そして、灌漑水田と天水田を合わせた栽培面積は全体の90%を超えている。
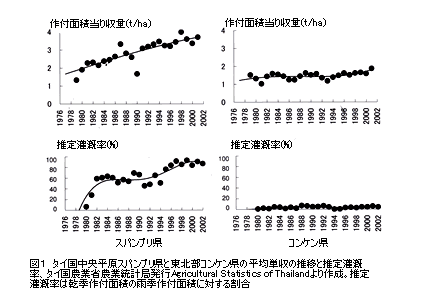
灌漑化は、アジア稲作における技術進歩の中で、もっとも重要な位置を占めてきた。灌漑の普及が生産力向上にいかに寄与するかは、タイの2つの対象的な地域を比較した図1によく表れている。チャオプラヤ川下流の中央平原に位置するスパンブリ県では,1980年以降、大規模プロジェクトによって灌漑水田率が急速に高まったが、それに同調して雨季作の作付面積当り籾収量(以下、単収)が着実に増加し、近年ではヘクタール当り4tに達しようとしている。日射条件に恵まれる乾季作では4.5t/haを超えることが多い。これに対して、タイ東北部は灌漑設備の整備が進まないままで取り残されている代表的な地域である。東北タイのコンケン県では、平均単収は1.5~1.8t/haという状態のままで今日に至っている。アジア稲作の技術の今後の展開も灌漑稲作と天水田稲作とでは、大きく異なると考えられる。以下、稲作の土地生産性の現在の到達点と今後の見通しについて、灌漑稲作と天水田稲作に分けて検討したい。
2.灌漑稲作
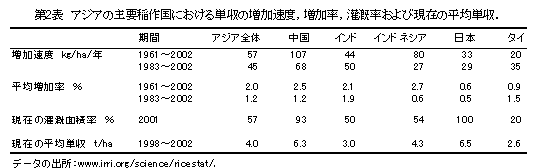
2-1 灌漑稲作における収量の到達点と増収可能性
1961年から2002年の42年間において、アジアのイネ単収は年当り57kg/ha、年率では約2.0%の割合で増加してきた(表2)。ただし、最近の20年間に限ってみると値はそれぞれ45kg/haおよび1.2%となり、増収ペースは鈍化する傾向にある。Cassman(2001)は単収の推移を主要国別に分析し、単収の伸びの停滞が著しい地域として、日本とインドネシアを挙げ、その要因として、早くから灌漑が発達し集約化も順調に進んできた結果、技術の進展によって増収できる余地が、次第に小さくなってきたことを指摘している。果たして、そうであろうか。アジアで灌漑率が100%で、単収がもっとも高い日本の到達点を点検してみた。
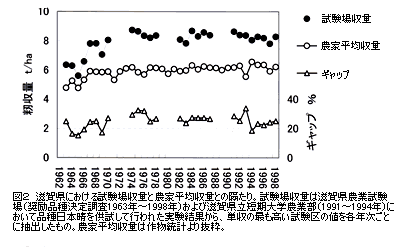
図2は滋賀県におけるイネの平均収量を、県内の農業試験場などにおいて品種日本晴を供試して行われた数々の栽培試験の中で、もっとも高かった試験区の収量と比較したものである。期間は日本晴が新品種として導入された1963年を始点に、それ以降である。これによると、滋賀県の平均収量は、1970年代前半に6t/ha台に達した後はわずかしか増加せず、停滞傾向が顕著になった。試験場収量は、導入後数年の間は、恐らく従来の品種よりも耐肥性に優れているこの品種に適した栽培法の確立により急速に高まり、1970年代に8t/haとなった。その後は同8tから8.5tの間を上下した。両者の隔たりを試験収量を基準とした割合で見ると、平均して約25%であった。
一方、わが国の気候下におけるイネ収量の可能最大値は上述の水準よりも高いと考えられている。堀江(1987)は水稲の生育収量の気象的予測モデル(SIMRIW)を開発し、それに新潟県から鹿児島県までの8か所の気候条件と多収性品種IR36の特性パラメータを与え、各地域の稲作の可能最大収量を試算した。あらゆるストレスが取り除かれると、作物群落の収量生産力は、基本的にその土地で利用できる日射エネルギーの積算量(日射量×日射受光率×生育期間)によって上限が決まる。受光エネルギーを光合成産を経て、植物体に変換する効率が種によって、一定の範囲にあることがよく知られているからである。ここでの可能最大収量は、各地の生育期間において、速やかな葉群の発達とその維持により日々の日射エネルギーが最大限捕捉され、群落による受光エネルギーの利用効率が高い値で維持され、かつ光合成産物の穂への分配率も品種固有の値を示す(低下しない)時に得られる収量である。仮定として、病害虫や低温・高温ストレスによる減収も起こらない。
このようにして決まる可能最大収量の地域差は、各地の県平均単収の違いと密接に連動していた。ただしその値は10t/haから13t/haと大きく、各地の平均単収の約2倍であった。これを参考にすると、滋賀県の場合では、収量の可能最大値はおよそ12.5t/haとなる。これに対して、試験場の上限収量(ただし日本晴)は約8.3t/ha、実際の農家平均収量は6.2t/haで安定あるいは停滞しているのが、わが国の滋賀県におけるイネ単収の現状である。
試験場の収量を可能最大値に近づけるためには、栽培管理の極端なまでの精密化が必要となる。それは1949年から68年にかけて行われた「米作日本一」表彰事業で競われた篤農技術が良い例になろう。受賞事例には籾単収が12t/haに達するような高収量が含まれており、ほぼわが国における可能最大収量に近い水準を示していると推察されるからである。米作日本一の稲作では、十分な水と養分が確保されているだけでなく、土つくり、施肥、水管理を周到に行い、理想生育を得るためのあらゆる手段が講じられていたという。そのために長年、栽培農家が耕地に注ぎ込む熱意と努力は並大抵ではなかった(鈴木、1993)。試験場収量が可能最大値に接近するには、このような超精密稲作が必要になると思われる。
それは不可能とはいえないが、少なくとも、再現性が十分にあり、広範な農家への普及が可能な技術として基準化することは難しい。それは、図2の試験場収量の推移自体によって、端的に示されている。つまり1970年以降、様々な技術内容の試験区が設けられたにもかかわらず、試験区中の最大値は常に一定の範囲に推移していることである。長年の間、試験場レベルでの品種日本晴の最高収量はある一定の水準、すなわち8.5t/ha、反当り玄米収量として約680kgを越えることはなかったわけである。よって、図2に示されているのは、現実的に達成可能な上限収量とみる必要がある。
農家平均収量と試験場収量との隔たりは、縮小するであろうか? 両者のギャップをもたらしている要因は多岐にわたっている。まず、県平均単収にはイモチ病が多発する山間地や瘠薄田など、不利な条件における単収も含まれている。それらを別にすると、生産技術の精密さの差異が重要であろう。
試験場での実験は当然のことながら条件を均質にして行われるが、それは種々の条件を良好なものに揃えることを意味する。実際の栽培では種子や苗の一部が、あるいは圃場のある部分が十分とはいえない条件で生産が行われることは通例である。水のかけ引き、施肥および雑草と病害虫防除のための薬剤散布といった管理作業を、もっとも適切な時期と方法で実施するのも、労力や資源に限りのある実際栽培では、ままならないことが多く、大規模化された経営では一層難しいであろう。また、実験における収量調査とは異なり、実際の収穫作業では2~3%程度のロスはよく生じる。これらの要素が重なって、試験場収量と農家平均収量との違いが生まれていると考えられる。
そして、図2は農家平均収量と上限収量とのギャップがおよそ30年の間に、わずかしか縮小しなかったことを如実に示している。この間に栽培技術の進歩がなかったわけではない。機械化やより効率的な除草剤の普及といった労働生産性の向上技術とともに、早植化ならびに施肥方法や育苗方法の改善など、数々の増収関連技術の開発と普及が行われてきた。にもかかわらず、その効果は農家平均収量を上限収量に著しく接近させるものでなかった。
その一方で、稲作を取り巻く社会状況の変化や、単収よりも品質が重視される傾向などから、増収を追求するインセンティブが弱くなってきたことも考えられるが、施肥量の増大のような、増収効果の大きい主要な技術改善は1970年代にほぼ達成されてしまい、新しい普及技術が増収効果を発揮する余地が次第に小さくなってきたのが、大きな要因と考えられる。
以上のことから、日本のような稲作先進国では、施肥などの増収効果の高い技術は既に普及が完了しており、平準化が困難な超精密な技術を別にすると、栽培技術の改善が農家平均収量の飛躍的な増収をもたらす可能性は小さくなってきていることを認めざるを得ないと思われる。
2-2 生産持続性に対する不安
水田稲作は、畑作に比べ一般に土壌浸食が起こりにくく、土壌肥沃度も維持されやすい。ところが、熱帯の集約化が進んできた地域では、水田稲作の生産性の持続に関する不安材料がたびたび指摘されている。
一つは虫害の発生である。日本でもウンカ・ヨコバイ類およびニカメイチュウの被害が問題となるが、熱帯アジアの稲作地帯では灌漑が整備され、集約化が進んだ地域で深刻である。特にトビイロウンカは東南アジア諸国で時々イネ生産に大打撃を与えてきた。図1のスパンブリ県のデータをみると、1990年の平均単収が大きく低下している。これは当年に大発生したトビイロウンカの被害であり、スパンブリを含む中部タイ諸県の平均単収が軒並み平年の半分以下に落ち込んだ(タイ国農業省害虫・害獣部、1996)。この時期は、図1にみられるように、灌漑率が急増し乾季作を含む2年5作の土地集約的な生産が普及してきた頃に当る。その結果、トビイロウンカにとってのホストが周年提供されることになり、それに施肥量の増加による稲体の栄養条件の改善があいまって、大発生を促したと考えられている。耐虫性品種の利用と適切な薬剤防除などにより、被害は抑えられてはいるが、最近(1998年)でも再び大発生をみている(Vungsilabutr、2001)。集約化による生産性の向上の結果として増大した虫害被害の問題は、まだ解決には至っていない。
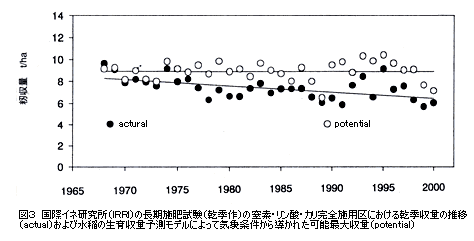
今ひとつは、土壌肥沃度の問題である。多毛作された水田の地力の経年的低下を示すデータが報告されている。図3はIRRIで1964年来行われている長期施肥試験から窒素、リン酸およびカリ肥量を十分に施した試験区の乾季作収量の推移を示したものである。当初は10t/ha近くあった収量が徐々に低下しており、近年では8t/haを確保するのも難しくなっている。図3では前述のSIMRIW(堀江、1987)を用い、窒素と水の制限がない場合のポテンシャル収量が、年々の気象条件にもとづいて推定されている(Padilla、2001)。その値は当地の気象生産力の推移を表しているが、それは年次変動を見せながらもトレンドとしては横ばいで経過してきた。すなわち、実収量の低下は気象以外の要因すなわち土壌の生産力の変化に起因することが明らかである。
Deweら(2000)は、熱帯から亜熱帯アジア地域で実施されてきたイネ栽培長期試験から、雨季作と乾季作を別に扱って、延べ52例のデータを検討した。それらは一定かつ十分な施肥条件下で10年間以上継続されたものである。11例で有意な単収低下の傾向がみとめられ、増加傾向を示したのは1例だけであった。単収低下の原因は未解明だが、窒素、リン酸、カリといった多量栄養素の供給能減退の可能性が高く、IRRIの試験区では、畑地休閑が挿入されない集約的な栽培の継続により、土壌の無機化窒素供給能が低下してきたと推察されている。そして、単収低下を示す試験例では、当初の単収レベルが高い傾向があった。図3のように、気象的可能最大収量に近い生産が数年間は実現できたとしても、それを長期間持続することは容易でないことを示している。
同様の地力低下の現象が日本の輪換水田でも起こっている可能性がある。近年、転換畑作ダイズの生育量と収量が畑作の累積期間が長いほど低化している傾向がみられるからだ(濱田ら、2003)。田畑輪換は、通常はイネと畑作物の両方の生産性にプラスに作用すると考えられているが、畑期間の割合がある程度以上大きくなると、土壌の窒素地力の消耗が起こり、イネの収量が低下してきたとする試験結果が報告されている(松村、2001)。
稲作が、地域によっては収量の可能最大値と比べ得るような高水準に達したのは、歴史的にみると最近のことに過ぎない。上述の問題を考慮すると、高い生産が長く持続できる保証はまだないとみるべきである。水田地力の実態の把握および変化の機構解明が、引き続き重要な課題になっている。
2-3 灌漑稲作の増収可能性
灌漑稲作の単収は、かつて我が国の米作日本一が実証したように、栽培管理を高度に精密化することで、可能最大値に近づくことができる。しかし、既に述べたように、広範な農家が実施可能な技術でもって、日本の単収が30年前に到達した水準を大きく越えることは非常に難しい。
収量限界への接近のもう一つの方法は品種選択である。収量性だけを目標にするならば、既にインディカの遺伝的背景を強く持つ多収品種が開発されている。ただし、通常の米飯用に使えるような食味品質を備えるにはほど遠い状態にあり、現段階では他用途利用目的の品種である。その中で、もっとも収量性が高い品種であるタカナリは、暖温帯の通常の栽培条件ではコシヒカリや日本晴などの実用品種と比べて、およそ25%から40%高い収量を示す(堀江ら、2003)。これによる増収を試験場収量に上乗せすると、現在わが国において達成可能な収量は可能最大値のおよそ80%程度になると思われる。およそ20%という隔たりは、IRRIにおいて、多収品種に十分な施肥を行った条件で得られる収量の当地における可能最大収量に対する隔たりとも一致しており(Horieら、1995)、通常考え得る栽培技術の範囲では超えることのむずかしい限界であろう。
品質が重視され、収量ポテンシャルが最高とは言えない品種が実用に供されているわが国では、逆に言えば、現在の品種とインディカ多収品種(タカナリもその一つ)との収量差の分だけ、増収余地が残されていると言えよう。
収量限界へのさらなる接近には、品種の収量ポテンシャルをさらに高めることであるが、IRRIでは、IR8の登場以来30年間以上進展がないことが指摘されている。遺伝的な収量ポテンシャルを高めるための研究は、それがどこまで可能かという検討も含めて重要な研究課題になっている。
3.天水田稲作
3-1 東北タイの天水田稲作の生産制限要因
アジアの稲作面積の中で灌漑が行われているのは全体の6割に満たない。灌漑化を阻んでいる事情は地域によって異なるが、社会・経済的要因に加えて水資源の制約や灌漑設備が整備されにくい地形的条件による制約も大きい。そういった地域では、天水稲作としての生産力の向上が必要となる。過去20年間において、東北タイ天水田地帯の単収は1年当り24kg/haの割合で増加してきた。この数字は、前述のスパンブリ県のように、灌漑化が進行中の地域に比べると、明らかに小さいが、東北部全体に共通する着実なものである。それには、ポンプを用いた部分灌漑の普及、水掛かりが安定している水田への施肥の増加、改良品種の採用などが貢献してきた。しかし、その実態に立ち入ってみると、本格的な灌漑が行われない限り増収には自ずと限界のあることが知らされる。
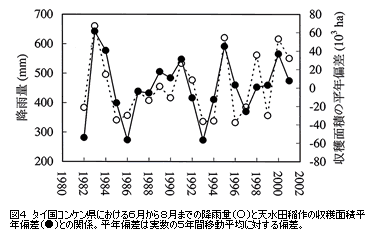
まず、天水田稲作の生産は降雨量に直接左右される。図4はコンケン県における収穫面積が雨季半ばの降雨量と密接な関係にあることを示している。コンケンのような天水田地帯の場合、雨季の初めに作付けられたイネが日本のように全て収穫されるわけではない。収穫面積率は作付後の降雨条件に左右されながら変動し、最終的に収穫面積と単収が生産量を決定する。そして、図の収穫面積に加えて作付面積と単収も、それぞれ雨季初期と雨季後期の県内雨量に強く左右されている(白岩ら、2001)。生産力が徐々に向上しているとは言え、天水田稲作は文字通り“天水”に強く依存しながら変動しているのである。
天水田稲作は土壌肥沃度によっても強い制約を受けている。ウボン・ラチャタニ県で行われた詳細な現地調査によると(Homma et al.、2003)、ノングと呼ばれる数百メートル四方の限られた範囲内に存在する水田の生産力には、その地形条件に応じて著しい変異が存在する。ノングは標高差数メートルの小規模で緩やかな傾斜を持つ盆地のことであるが、その中で相対標高に沿って下位から上位へ向かうほど土地生産性は低くなる。一見、水掛かりの条件が生産性を決めているようにみえるが、相対高度の異なる水田の土壌の養分供給力を、十分な灌水を行ったポット栽培によりバイオアッセイ(生物学的定量)しても、本田の生育と相関する著しい地力差が認められた。これは土壌肥沃度の違いが水条件に比べて、より直接的な生産力支配要因になっていることを示しており、土壌分析などの結果から粘土含量および有機炭素含量の違いが重要であることがわかった。
もともとの地力が低い上に不安定な降雨に頼らざるを得ない状況下では、資源や労力の投入量を増やしたとしても、それに見合う収穫が得られる確証がなく、東北タイ天水田地帯の平均単収が伸び悩むのは当然のように思われる。
3-2 天水田稲作の増収に向けて
天水田に多収性品種を導入する効果はあるだろうか。東北タイのウボン稲試験場において、現地型に近い未改良の長稈品種と短稈で収穫系数の高いインディカ多収品種との間で収量形成過程を比較した(図5)。
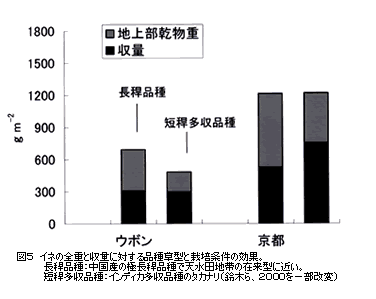
その結果、収量では両者の間に差異がないがバイオマス収量は明らかに長稈型が優っていた。同じ2品種を肥沃な京都の圃場で栽培すると、インディカ多収品種の方が持つ多収性が明瞭であった(鈴木ら、2000)。
つまり、イネの収量は遺伝子・環境相互作用の影響を受け、天水田稲作では灌漑条件での多収性品種が必ずしも有利とは限らない。とりわけ東北タイ天水田地帯では、土壌の有機物含量が土地生産性を左右する要因となり、イネ体残渣は貴重な土壌有機物源となっている。また、天水田では干ばつだけでなく洪水害も発生することがあり、その面からも長稈の特性が有利と言える。このように土壌肥沃度が低く、かつ変動の大きい環境に適応するためには、固定したエネルギーを最大限穀実に振り向ける多収性品種とは異なる品種特性が必要となる。天水田稲作において、多収性品種に多くの施肥を施すことで単収を高められる場面は、安定した水分環境に恵まれている水田に限定されるようである。
生産力拡大をもたらす可能性が高い技術課題を挙げるとすれば、それは地力の改善であろう。筆者らの研究室では、タイ東北部のウボン稲試験場において、天水田の土地生産性の改善を目指して乾季休閑期間に緑肥マメ化作物を生産したり、乾季に干上がるため池の底泥を天水田に客土する試みを行っている。そして、特に後者の効果が明瞭になりつつあり、約30mmの厚さの客土を施すだけで、客土後3年間を通じて土壌の保肥力が顕著に改善され、イネの増収が明らかに認められた(望月ら、未発表)。
4.終わりに
灌漑稲作と天水田稲作はともに、それぞれの条件で採用が可能な技術を適切に実行することにより、あるいは労力や資源が許す範囲で管理を精密化することにより、増収できる場面が多々ある。しかし、ある程度まで増収すると、超えることの難しい限界が存在するのも事実である。このうち灌漑稲作に関しては、品種の収量ポテンシャルが格段に向上すれば、生産性の拡大に新しい局面が生じると期待され、多収性品種開発の重要性は引き続き大きいと考えられる。しかし、その一方で、高い生産性を長く持続させるための耕地管理のあり方が十分に留意されなければならない。アジアにおける潜在耕地の枯渇が懸念されている中、土壌生産力の維持・増進は、灌漑稲作と天水田稲作の両方にとって、極めて重要な課題と考える。
《引用文献》
Dawe, D., Dobermann, A., Moya, P., Abdulrachman, S., Bijay Singh, Lal,
P., Li, S.Y., Lin, B., Panaullah, G., Sariam, O., Singh, Y., Swarup,
A., Tan,
P.S. and Zhen, Q.X. 2000. How widespread are yield declines in long-term
rice experiments in Asia? Field Crops Research 66: 175-193.
Cassman, K.G. 2001. Crop science research to assure food security. J. Nosberger,
H.H. Geiger and P.C. Struik eds. Crop Science: Progress and Prospects. CAB
International, Wallingford. 33-51.
濱田千裕・池田彰弘・谷俊男・武井真理・落合幾美・釋一郎 2003.愛知県におけるダイズ収量改善技術の開発と効果.日作紀72(別1):58―59.
Homma, K., Horie, T., Shiraiwa, T., Supapoj, N., Matsumoto, N. and Kabaki,
N. 2003. Toposequential variation in soil fertility and rice productivity
of rainfed lowland paddy fields in mini-watershed (Nong) in Northeast Thailand.
Plant Prod. Sci. 6: 147-153.
Horie, T., Nakagawa, H., Centeno, H.G.S. and Kropff, M.J. 1995. The rice
crop simulation model SIMRIW and its testing. R.B. Matthews, M.J. Kropff,
D. Bachelet
and H.H. Van Laar eds., Modelling The Impact of Climate Change on Rice Production
in Asia. CAB international, Oxon, UK. 51-66.
堀江武・吉田ひろえ・白岩立彦・中川博視・黒田栄喜・佐々木忠勝・萩原素之・小葉田亨・大西政夫・小林和弘 2003.アジア広域環境下におけるイネの生育・収量形成の遺伝子型・環境相互作用の解析.1.アジアイネネットワーク試験(ARICENET)での生育・収量の遺伝的・環境的変異.日作紀72(別2):88-89.
松村修 2001.田畑輪換技術の開発とその問題点.日作紀70(別2):377―382.
Padilla, J. 2001. Analysis of long-term changes in rice productivity under
intensive cropping systems in the tropics and improvement of nitrogen use
efficiency. PhD thesis, Kyoto University. 1-157.
Penning de Fries, F.W.T. 2001 Food security? We are losing ground fast! J.
Nosberger, H.H. Geiger and P.C. Struik eds. Crop Science: Progress and Prospects.
CAB International, Wallingford. 1-14.
白岩立彦・中川博視・堀江武・松井勤・本間香貴:タイ稲作の生産変動実態ならびに降雨量が生産変動に及ぼす影響.地球環境6:207-215、2001.
鈴木守 1993.農民に学ぶ技術の総合化―多収穫栽培技術―.農水省農林水産技術会議事務局昭和農業技術発達史編纂委員会編、昭和農業技術発達史水田作編第3章第3節.農文協、東京.124-135.
鈴木辰徳・白岩立彦・本間香貴・堀江武 2000.草型の異なるイネ品種の乾物生産における窒素利用効率とその土壌肥沃度反応.日作紀69(別2):24-25.
タイ国農業省害虫・害獣部 1996.トビイロウンカの被害と対策―1991~1996年プロジェクト(タイ語).バンコク.1-189.
Vungsilabutr, P. 2001. Population management of the rice brown planthopper
in Thailand. Proc. Inter-Country Forecasting System and Management for Brown
Planthopper in East Asia, 13-15 Nov., Hanoi.