
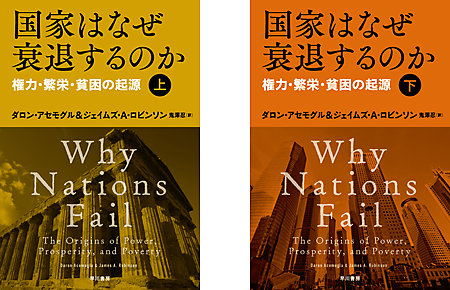
地球上に豊かな国と貧しい国の両方が存在するのはなぜか、不平等の原因は何か ── 本書はその問いに答えるために書かれた。たとえば、国境を挟んで隣り合うアメリカのアリゾナ州ノガレスとメキシコのソノラ州ノガレス。前者では、平均的世帯の年収は3万ドルで、大半の大人は高校を卒業している。市民は比較的健康で、法と秩序が保たれているために、命や安全について心配することはない。しかし、後者では、平均的世帯の収入は前者の3分の1。大人のほとんどは高校を卒業していないし、乳児死亡率は高い。犯罪率が高く、政治家は腐敗している。同じ先祖と同じ文化を持つ二つのノガレスがこれほど違うのは、ある時期に町が二つの国に分かれ、異なる制度によって異なる世界が形づくられたからだ。
世界の不平等を説明する理論には、(1)気候、地理、病気などが経済的成功を左右するという「地理説」、(2)宗教、倫理、価値観などを国の繁栄と結びつける「文化説」、(3)貧しい国が貧しいのは統治者が国を裕福にする方法を知らないからだとする「無知説」 ── などがある。しかし、著者はこれらをいずれも否定し、繁栄と貧困を分けるのは政治と経済における「制度」だと強調する。
国家の制度は、権力が社会に広く配分され大多数の人々が経済活動に参加できる「包括的制度」と、限られたエリートに権力と富が集中する「収奪的制度」に分けることができる(「包括的」という言葉はやや分かりにくいが、一般的な感覚では「民主主義的」に近いだろう)。包括的制度のもとでは、法の支配が確立し、所有権が保護され、イノベーションが起こりやすい。収奪的な政治制度と経済制度のもとでは、その反対のことが起きる。そして、「経済的な成長や繁栄は包括的な経済制度および政治制度と結びついていて、収奪的制度は概して停滞と貧困につながる」と著者は主張する。
おおむね以上が本書の結論であり、第1章から第3章まででほぼ語られている(全体は計15章)。第4章以降では、そのような包括的制度と収奪的制度が歴史のなかで、どのように形成されてきたかを、以下のように数多くの事例を挙げながら検証している。
・14世紀以前のヨーロッパでは、農民の力が東よりも西欧で少しだけ強かった。そのため、1346年のペスト襲来という「決定的な岐路」を経て、西欧では封建制が崩壊に向かい、東欧では農奴制が再構築された。イングランドの王の支配力はフランスやスペインよりも弱かったため、1600年以降の大西洋貿易拡大によって、イングランドでは多元的な新しい制度が生まれ、フランスとスペインでは君主制が強化された。このように、もともとあった制度の小さな相違が、ペストや大西洋貿易といった「決定的な岐路」と相互作用を起こすことによって、経済発展の異なるパターンが決まる。(第4章)
・収奪的制度のもとでも経済成長が起きることがある。たとえば、ソ連が急速な成長を達成できたのは、ボルシェビキが強力な中央集権国家を築き、資源を工業に配分したからだ。しかし、収奪的制度では個々人の才能やアイデアが活用されないため技術的発展が生まれず、成長は長続きしない。(第5章)
・産業革命がイングランドで始まり大きく前進したのは、1688年の名誉革命が包括的政治制度をもたらしたためだった。所有権が強化され、金融市場が改善され、海外貿易での国家承認専売制度が弱められて、産業拡大の障壁が取り除かれた。一方、スペイン、オーストリア・ハンガリー帝国、オスマン帝国、ロシア、中国などでは専制君主が収奪的制度を確立し、産業革命の流れに乗り遅れた。これらの国では支配者が創造的破壊を恐れ、経済成長をあえて促さなかった。また、東南アジアやアフリカは、ヨーロッパの植民地帝国に収奪的制度を押しつけられ、発展の可能性をつぶされた。(第7章~第9章)
・名誉革命後のイギリスや、19世紀末から20世紀初めのアメリカでは、包括的な政治・経済制度が維持され拡大する「好循環」が生じた。逆に、多くの国で収奪的制度の「悪循環」が起きた。グアテマラやアメリカ南部では、同じ種類のエリートが長期間にわたって権力を握り、シエラレオネやエチオピアでは、独裁者を打倒して統治を引き継いだ人々が同じように権力を乱用した。現代においても、ジンバブエ、コロンビア、北朝鮮、ウズベキスタンなど多くの国で収奪的制度の悪循環が繰り返されている。(第11章~第13章)
・中国では文化大革命の後、鄧小平のもとで包括的経済制度へ向かう改革が行われ、目を見張るばかりの成長が実現した。だが、成長の基盤は創造的破壊ではなく、既存のテクノロジーの利用と急速な投資だった。収奪的な政治制度から包括的政治制度への移行がなければ、中国の成長はいずれ活力を失うだろう。(第15章)
豊かな国をつくるには包括的制度の発展が不可欠だという本書の主張はきわめてシンプルで、分かりやすい。民主政治と自由な市場経済が国の繁栄の前提条件だという視点は、先進資本主義国に住む人々の実感にも近い。豊富な歴史的事実の記述が、説得力を持って「制度説」を裏づけているように思える。
では、収奪的制度から包括的制度に移行するにはどうすればよいか。著者は「移行をたやすく達成する処方はない」と言い切る。欧米諸国や国際機関が貧しい国に対して行ってきた経済政策の提案や援助は、いずれも効果的ではなかったという。第15章の最終節で、包括的制度の強化に成功した国に共通するのは「社会のきわめて広範かつ多様な集団への権限移譲に成功したことだ」と指摘している。困難ではあっても、各国の内側で政治的な多元主義が育つのを期待するしかないということだろう。納得できる見解といえる。
ただ、そのうえで語ってほしかったのは、包括的制度を他に先立って実現した国々の「責任」についてである。貧しい国の収奪的制度はその国自身の歴史のなかで形成されたものだが、多くの場合、その過程で他国との「関係」が作用していた。本書でも、東南アジアやアフリカに対する植民地支配が収奪的制度の固定化につながったことが語られているが、もっとも多くの植民地を持ったのは民主主義の最先進国・イギリスだったはずだ。20世紀の東西冷戦と、冷戦終了後に異常に拡張したグローバル経済も、貧しい国の収奪的制度を豊かな国が利用することによって成立したという側面がある。本書は主に一国内の収奪的制度に着目しているが、国際的な収奪構造も無視するわけにいかない。だとしたら、先進国の側も貧困の克服のために、従来とは異なる関与の仕方を探るべきではないだろうか。
*早川書房刊 本体価格=上下巻各2400円